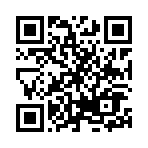カテーテル検査してきました その2
2016年09月20日
2泊3日の検査入院で、初日が一番忙しかったです
朝の6時半に家を出発して、
11時半頃に病院に到着
12時前に病棟へ
身長、体重計測
(昼ごはん)
CT、MRIの事前説明、CTの同意書
検温、血圧、サチュレーション
心電図
(シャワー)
採血
MRI、CT
(夕ごはん)
エコー
カテの事前説明、カテの同意書
MRIとCTに1時間半弱かかりました~
小児科医からカテの説明を受けたのが、消灯後の20時半
もうすぐ15歳になるので、子どもも一緒に説明を聞きました
そうそう、うちの子の主治医は基本は別の病院に勤務していて、
榊原には第一、第三土曜しか来ません
なので、今回の担当は、別の先生・・・
でも最初の手術の時からいてくれた先生で、
一時は主治医になってくれてた時もあって、
良く知っている先生なので、安心でした
で、
説明を聞いていたのですが、、、
うちの子、「血管」などの単語に弱くて、、、
先生の話を聞きながら、顔面蒼白に・・・
先生も様子を見て、
もっと詳しく説明するはずだった今までの手術の経緯は
少し端折ってくださいました
でも、うちの子、
カテの説明の大事なところはちゃんときいてました
わたしよりちゃんと聞いてたかも??
えらいなあ~
まあ自分のことだから、そりゃあ真剣に聞いとかなくてはね、、、
2日目がカテ―テル検査
2例目で予定は10時半から
朝の4時半に食事止め
7時半に水分止めでした
検温、血圧、サチュレーション、
採血
10時に眠り薬を飲みましたが、ちっとも眠くならず。。。
しっかり覚醒したまま、
11時カテ室へ
12時半に病棟に戻ってきました
すでに麻酔からは覚めてました
そして、、、
18時半まで6時間ベッドの上で動けません
点滴
検温、血圧
(昼ごはん)
小児科医からカテの結果のおはなし
(本当は子どもも一緒がよかったようですが、昨日の気分が悪くなった様子から、わたしひとりで聞きました)
カテ自体は麻酔で眠っている間に終わるのですが、
その後、麻酔が覚めてから、
動いてもいいと許可がでるまでの安静6時間が一番キツイようです
検査のために、
右足付け根から動脈、静脈両方に管を入れたので、
しっかりテーピングされたうえで、
動いてはダメ!と・・・
小さい子だと、
「動いちゃだめ」と言うだけではもちろん動いてしまうので、
物理的に動けないように、
腰から膝くらいまで板をつけて足を伸ばしておくのですが、
うちの子のように大きくなると、
板はつけずに、自分の意思で動かさないようにします
多少動かそうと思えば動くようですが、
なにせ傷口を圧迫してるし、テープもきついしで、
けっこう痛いらしく、
やむを得ず動く以外は、
わざわざ動くことはなかったです
そういえば、赤ちゃんの時、
足の付け根を動かさないように板をつけたままだっこして、
動けなくて泣くのをなだめたりして、
親はしんどかったなあって、思いだしましたが、
本人も気持ちを伝えられないだけで、とってもきつかったんだろうな~と
いまさらながら思いました
ヒマだ暇だ、と繰り返してました
横になってるので、
ヒマつぶしに持ってきた塗り絵はできない、
本(マンガ)を読もうにも、手がいたくて持てない、
寝たら時間がすぐ経つのに眠れない、
寝られてもすぐ目が覚める、、、
待つ時間は1分がと~っても長く感じる、、、
テレビのプリペイドカードを買えばよかったね~
テレビがあったら少しは気が紛れたかも、、、
次の時はそうしようね~ってはなしました
結局2時間くらいは寝れたのかな?
あとはヒマ~
そんな我慢我慢の6時間を過ごして、
動かして良くなっても、
今度は傷のところを、きっちりびっちりテーピングしてあって、
それが痛くて動きにくい。。。
麻酔の支柱?を杖代わりに持って、トイレまで移動したり、
ベッドで起き上がるところから、立ったり座ったりも思うように動けずに、
いろいろ大変だったようです
(夕ごはん)
(体拭き、着替え)
血圧、検温
点滴外し
いろいろ大変な一日だったので、早目に寝ました
翌日は退院日
カテの結果がよかったので、予定通り退院です
朝から帰り支度をして待ちました~
足の付け根のテーピングは朝外してもらいました
そうそう、ちょうど第三土曜だったので、
主治医も病棟に来てくれて会えました
やっぱり長年のつきあいなので、気楽に話ができます
さて、カテの結果は、良好でした
肺動脈が一部狭窄してバルーンをしたところは狭窄が残っていますが、
他は
心室機能も心房機能もバランスよく良好、
弁の逆流も問題なし、
最初の手術で縫い合わせたところも狭窄なし、
酸素飽和度95.5%でチアノーゼなし、
グレン、フォンタン術後の血管も血流スムーズで狭窄なし、
側副血管も問題なし、
などなど、
説明してもらえました
MRIやCTの解析結果は次の診察時だそうです
フォンタン術後10年は、よい状態ということでした
そしてこれから先、
この状態を保っていくことが大事、
ということで、
ワーファリンが1錠から2錠に増えて、
心臓の働きを助ける薬が増えました
カンデサルタンOD2mmgという薬が1錠
バイアスピリン1錠もあるので、
全部で4錠です
よい状態なのに、薬が増えるのか~
ため息、、、
薬が増えるのはちょっと気が重いです・・・
でも、
心臓は長持ちしてもらいたいから、
少しでも心臓の働きの助けになるなら、
と、前向きに
次は、新しい薬の様子見もあるので、
冬に診察に行こうかと思っています
予約しておこうっと
朝の6時半に家を出発して、
11時半頃に病院に到着
12時前に病棟へ
身長、体重計測
(昼ごはん)
CT、MRIの事前説明、CTの同意書
検温、血圧、サチュレーション
心電図
(シャワー)
採血
MRI、CT
(夕ごはん)
エコー
カテの事前説明、カテの同意書
MRIとCTに1時間半弱かかりました~
小児科医からカテの説明を受けたのが、消灯後の20時半
もうすぐ15歳になるので、子どもも一緒に説明を聞きました
そうそう、うちの子の主治医は基本は別の病院に勤務していて、
榊原には第一、第三土曜しか来ません
なので、今回の担当は、別の先生・・・
でも最初の手術の時からいてくれた先生で、
一時は主治医になってくれてた時もあって、
良く知っている先生なので、安心でした
で、
説明を聞いていたのですが、、、
うちの子、「血管」などの単語に弱くて、、、
先生の話を聞きながら、顔面蒼白に・・・
先生も様子を見て、
もっと詳しく説明するはずだった今までの手術の経緯は
少し端折ってくださいました
でも、うちの子、
カテの説明の大事なところはちゃんときいてました
わたしよりちゃんと聞いてたかも??
えらいなあ~
まあ自分のことだから、そりゃあ真剣に聞いとかなくてはね、、、
2日目がカテ―テル検査
2例目で予定は10時半から
朝の4時半に食事止め
7時半に水分止めでした
検温、血圧、サチュレーション、
採血
10時に眠り薬を飲みましたが、ちっとも眠くならず。。。
しっかり覚醒したまま、
11時カテ室へ
12時半に病棟に戻ってきました
すでに麻酔からは覚めてました
そして、、、
18時半まで6時間ベッドの上で動けません
点滴
検温、血圧
(昼ごはん)
小児科医からカテの結果のおはなし
(本当は子どもも一緒がよかったようですが、昨日の気分が悪くなった様子から、わたしひとりで聞きました)
カテ自体は麻酔で眠っている間に終わるのですが、
その後、麻酔が覚めてから、
動いてもいいと許可がでるまでの安静6時間が一番キツイようです
検査のために、
右足付け根から動脈、静脈両方に管を入れたので、
しっかりテーピングされたうえで、
動いてはダメ!と・・・
小さい子だと、
「動いちゃだめ」と言うだけではもちろん動いてしまうので、
物理的に動けないように、
腰から膝くらいまで板をつけて足を伸ばしておくのですが、
うちの子のように大きくなると、
板はつけずに、自分の意思で動かさないようにします
多少動かそうと思えば動くようですが、
なにせ傷口を圧迫してるし、テープもきついしで、
けっこう痛いらしく、
やむを得ず動く以外は、
わざわざ動くことはなかったです
そういえば、赤ちゃんの時、
足の付け根を動かさないように板をつけたままだっこして、
動けなくて泣くのをなだめたりして、
親はしんどかったなあって、思いだしましたが、
本人も気持ちを伝えられないだけで、とってもきつかったんだろうな~と
いまさらながら思いました
ヒマだ暇だ、と繰り返してました
横になってるので、
ヒマつぶしに持ってきた塗り絵はできない、
本(マンガ)を読もうにも、手がいたくて持てない、
寝たら時間がすぐ経つのに眠れない、
寝られてもすぐ目が覚める、、、
待つ時間は1分がと~っても長く感じる、、、
テレビのプリペイドカードを買えばよかったね~
テレビがあったら少しは気が紛れたかも、、、
次の時はそうしようね~ってはなしました
結局2時間くらいは寝れたのかな?
あとはヒマ~
そんな我慢我慢の6時間を過ごして、
動かして良くなっても、
今度は傷のところを、きっちりびっちりテーピングしてあって、
それが痛くて動きにくい。。。
麻酔の支柱?を杖代わりに持って、トイレまで移動したり、
ベッドで起き上がるところから、立ったり座ったりも思うように動けずに、
いろいろ大変だったようです
(夕ごはん)
(体拭き、着替え)
血圧、検温
点滴外し
いろいろ大変な一日だったので、早目に寝ました
翌日は退院日
カテの結果がよかったので、予定通り退院です
朝から帰り支度をして待ちました~
足の付け根のテーピングは朝外してもらいました
そうそう、ちょうど第三土曜だったので、
主治医も病棟に来てくれて会えました
やっぱり長年のつきあいなので、気楽に話ができます
さて、カテの結果は、良好でした
肺動脈が一部狭窄してバルーンをしたところは狭窄が残っていますが、
他は
心室機能も心房機能もバランスよく良好、
弁の逆流も問題なし、
最初の手術で縫い合わせたところも狭窄なし、
酸素飽和度95.5%でチアノーゼなし、
グレン、フォンタン術後の血管も血流スムーズで狭窄なし、
側副血管も問題なし、
などなど、
説明してもらえました
MRIやCTの解析結果は次の診察時だそうです
フォンタン術後10年は、よい状態ということでした
そしてこれから先、
この状態を保っていくことが大事、
ということで、
ワーファリンが1錠から2錠に増えて、
心臓の働きを助ける薬が増えました
カンデサルタンOD2mmgという薬が1錠
バイアスピリン1錠もあるので、
全部で4錠です
よい状態なのに、薬が増えるのか~
ため息、、、
薬が増えるのはちょっと気が重いです・・・
でも、
心臓は長持ちしてもらいたいから、
少しでも心臓の働きの助けになるなら、
と、前向きに
次は、新しい薬の様子見もあるので、
冬に診察に行こうかと思っています
予約しておこうっと
カテーテル検査してきました その1
2016年09月20日
9.15-17まで、子どものカテーテル検査入院に東京まで行ってきました

入院したのは、東京・調布にある榊原記念病院
滋賀からは遠いですが、
滋賀に来る前、
子どもの手術を榊原でしていたのと、
最初の手術から診てくれている主治医も榊原にいるので、、、
そうそう、
榊原記念病院はうちの子が生まれた15年前はまだ新宿にありました
うちの子、
横浜・青葉区の先生ひとりの産院で生まれて、
2日後には心臓の異常が見つかって、
救急車で川崎の聖マリアンナ医大病院へ連れて行かれ、
そこでは処置できないということで、
また救急車に乗せられて、
夜の渋滞した首都高をサイレンならして、
新宿の榊原へ・・・
退院まで家にいてくれてた義母が聖マリへ付き添ってくれて、
聖マリで義母は父さんとバトンタッチ
榊原へは父さんが行ってくれました
私は産院で救急車に乗せられて運ばれていく子を見送って、
そのままひとりで、
急転直下の展開に心がついていけずに、
ひたすら連絡を待っていたのを覚えています
もうすぐ15年になるのだけど、やっぱり忘れてないな~
そうしてそうして、
生後5日の子どもは無事に最初の手術を乗り切ってくれたのでした
そうして、今があるんです
まあ、いいわけになってしまうけど、
最初のショックがあまりに大きかったので、
15歳も間近だというのに、
ついついいらない心配をしてしまうんですよね~
で、
3回目の手術までは新宿で、
4回目のTCPC手術の時は、
調布に移転して建て替わった新しい病院でした
それが3歳の時
それから10年以上経っているので、「そろそろなかを見てみましょう」、
ということで、今回のカテーテル検査になったのでした
カテのことは1年前くらいから言われていて、ドキドキ、、、
10年前まだ新しかった病棟は良い感じにこなれてて、
病棟のスタッフもすっかり変わってました
でもスタッフの忙しさは前と変わらないですね~
小児病棟で、心臓専門病院なので、
どの子も心疾患の手術または検査の入院で、
基本的にお母さんがつき添って子どもの世話をしていますが、
スタッフはあっちこっち呼ばれて走り回ってました
うちの子14歳(あと1か月で15歳)で、
夏休みも終わってる時期なので、
学童はほかにいなくてひとり、
ほかは新生児から、3~4歳位までの子ばかりでした
満床だったらしいです
さてさて、
病室は4人部屋
けっこう広いスペースです
窓側だったので明るいです
壁は空色に塗ってあって、雲の絵が描かれています


小児病棟に入院するのは15歳までと聞いているので、
これがたぶん最後になるだろうということで記念(?)に撮りました
付き添いもこれが最後かな~?
つづく・・・
入院したのは、東京・調布にある榊原記念病院
滋賀からは遠いですが、
滋賀に来る前、
子どもの手術を榊原でしていたのと、
最初の手術から診てくれている主治医も榊原にいるので、、、
そうそう、
榊原記念病院はうちの子が生まれた15年前はまだ新宿にありました
うちの子、
横浜・青葉区の先生ひとりの産院で生まれて、
2日後には心臓の異常が見つかって、
救急車で川崎の聖マリアンナ医大病院へ連れて行かれ、
そこでは処置できないということで、
また救急車に乗せられて、
夜の渋滞した首都高をサイレンならして、
新宿の榊原へ・・・
退院まで家にいてくれてた義母が聖マリへ付き添ってくれて、
聖マリで義母は父さんとバトンタッチ
榊原へは父さんが行ってくれました
私は産院で救急車に乗せられて運ばれていく子を見送って、
そのままひとりで、
急転直下の展開に心がついていけずに、
ひたすら連絡を待っていたのを覚えています
もうすぐ15年になるのだけど、やっぱり忘れてないな~
そうしてそうして、
生後5日の子どもは無事に最初の手術を乗り切ってくれたのでした
そうして、今があるんです
まあ、いいわけになってしまうけど、
最初のショックがあまりに大きかったので、
15歳も間近だというのに、
ついついいらない心配をしてしまうんですよね~
で、
3回目の手術までは新宿で、
4回目のTCPC手術の時は、
調布に移転して建て替わった新しい病院でした
それが3歳の時
それから10年以上経っているので、「そろそろなかを見てみましょう」、
ということで、今回のカテーテル検査になったのでした
カテのことは1年前くらいから言われていて、ドキドキ、、、
10年前まだ新しかった病棟は良い感じにこなれてて、
病棟のスタッフもすっかり変わってました
でもスタッフの忙しさは前と変わらないですね~
小児病棟で、心臓専門病院なので、
どの子も心疾患の手術または検査の入院で、
基本的にお母さんがつき添って子どもの世話をしていますが、
スタッフはあっちこっち呼ばれて走り回ってました
うちの子14歳(あと1か月で15歳)で、
夏休みも終わってる時期なので、
学童はほかにいなくてひとり、
ほかは新生児から、3~4歳位までの子ばかりでした
満床だったらしいです
さてさて、
病室は4人部屋
けっこう広いスペースです
窓側だったので明るいです
壁は空色に塗ってあって、雲の絵が描かれています
小児病棟に入院するのは15歳までと聞いているので、
これがたぶん最後になるだろうということで記念(?)に撮りました
付き添いもこれが最後かな~?
つづく・・・
心臓病管理指導表
2016年05月30日
先週末、子どもの診察のため、東京の病院に行ってきました
心臓専門の病院です
いちおう3か月に1度は診察に来てねと言われていますが、
東京で遠いので、半年に一度になっています
薬が90日分しか出ないので、なくなったら滋賀医大にも行っています
もうすでに生活基盤は滋賀になっているので、
本当は関西で主治医を見つけて診ていただくのがいいのかな~とは思うのですが、
生まれてすぐの手術から診てくださっている主治医がいる病院を変わるのは勇気がいります
最初の手術からはもう14年過ぎているので、
病院の他の医師はほとんど変わってしまっているようですが、、、

学校生活をしていると、
新学期にはかならず面談とともに「心臓病管理指導表」というのを提出します
今回診察に行って主治医に書いてもらいました
うちは今は学校に行っていないので、形だけの提出になっていますが、
学校の先生方は「管理指導表」に基づいて、
体育の授業や行事の参加などを考慮してくださいます
その都度相談したり、保護者がつき添ったり、ということも多いようです
同じ病名でも症状は個人でまったく異なり、まして心疾患の病名はたくさんあるので、
(自分の子どもの病名だけでも難しいです)
管理指導表があっても、個人個人で学校と相談しながら学校生活を送る必要があります
学校側も何かあったら大変なので、そのあたりはプレッシャーかもしれません
でも、「何かあると怖いから」、「困るから」、というような理由で、
何もさせてもらえない、という事例もあるようです
それでは、本来子どもができるであろう経験を奪ってしまうことになりかねず、
どこまでできて、どこまでできないかは、実際体験してみないとわからないことなので、
様子を見つつ、いろんな経験をさせてあげてほしいと思います

かく言うわたしも、
やっぱり子どもが小さかった頃は、
(いや、わりと最近まで、)
どうしても心配で、子どもの行動にいろいろと制限つけてました
小さい頃は毎日公園で遊ばせるというのは日課にしてましたが、
(多少の雨でもカッパ着せて連れてってました)
体を動かすこと、疲れそうなこと、はなるべくさせず、、、
だから公園までの行き帰りはベビーカーでしたし、
走りたそうなのを走らないで歩かせたり、
歩くの疲れたそぶりを見せたらすぐにだっこしたり、
いつもいつも子どもの行動を気にしていました
結局、本来できたかもしれない経験をしてこなかったことが多く、
経験値が足りないことで、
少し大きくなってから、本人がいろんな場面で、
困ったり、自信が持てなかったり、という原因になってしまったかな、
と反省です
今は成長して、自分の体調をだいぶ説明できるようになってきたので、
ずいぶん安心です
経験という面では遅ればせながら、本人がしたいと思うことは制限せずに、
できる限り経験できるようにと思っています
乗馬もそのひとつです

主治医からは、
走るよりも歩くことが大事、たくさん歩いてね、と言われています
足は第二の心臓で、歩くことによって心臓の循環の助けになります
うちの子の心臓の状態だと、
心臓のポンプの力を借りずに血液循環がされている(だらだらと流れ続けている)ので、
とくに足などは血流が戻りにくいのですが、
歩くこと、足を使うことが血流を押し上げる力になるようです
乗馬の良いところは、やっぱり足を使ってることかなと思います
体幹も鍛えられているようですし
乗馬をする前は、体がふにゃふにゃしてる感じだったのですが、
馬に乗るようになって、ふにゃふにゃ感がなくなりました
それに、大きな動物と意思を通わせることで、いろんな学びがあるようです
乗馬に出会えてよかったな~って本当に思います

ちなみに、子どもの管理指導表の指導区分はDです
Dは中等度の運動は「可」
・・・・
「中等度の運動」とは、
同年齢の平均的生徒にとって、少し息が弾むが息苦しくはない程度の運動
パートナーがいれば楽に会話ができる程度の運動であり、原則として、身体の強い接触を伴わないもの
等尺運動は「強い運動」ほどの力を込めて行わないもの
・・・・
「強い運動」とは、
同年齢の平均的生徒にとって、息が弾み息苦しさを感じるほどの運動
等尺運動の場合は、動作時に歯を食いしばったり、大きな掛け声を伴ったり、動作中や動作後に、顔面の紅潮、呼吸速迫を伴うほどの運動
・・・・

要するに心臓に負担がかかるかどうか、というところだと思います
Dなので、短距離走、長距離走、競泳、遠泳、球技の試合などは、
しないほうがいい、という感じでしょうか
でも例えば運動会で走りたいと思っているようなら、
スタート位置をずらすとかの考慮をしてもらって走ることで、
本人の参加したいという気持ちが納得できたら、
それも自信につながるのかなとは思います
どうしても運動系には自信を持てないことが多いですから、、、
まあ、うちの子は走りたい子ではなかったので、走ってませんが、、、

そんなこんなで、次回診察の9月はカテーテル検査で2泊3日の入院です
3歳の時のTCPC手術以来なので、どうなることやら、、、
今回エコーで確認してもらった心臓の状態は良好なようですし、
特に何か問題があるからカテをするわけではなく、
手術から10年以上たっているので、
外からはわからない、なかの状態を見てみましょう、
ということらしいです
あとは側副血管ができていたらコイルを詰めるそうです
側副血管は心臓の負担になるようなので
将来のリスクを減らすためにできることはしておきましょう
この子の心臓なら長生きできるよ~
と主治医

ありがとうございます
心臓専門の病院です
いちおう3か月に1度は診察に来てねと言われていますが、
東京で遠いので、半年に一度になっています
薬が90日分しか出ないので、なくなったら滋賀医大にも行っています
もうすでに生活基盤は滋賀になっているので、
本当は関西で主治医を見つけて診ていただくのがいいのかな~とは思うのですが、
生まれてすぐの手術から診てくださっている主治医がいる病院を変わるのは勇気がいります
最初の手術からはもう14年過ぎているので、
病院の他の医師はほとんど変わってしまっているようですが、、、
学校生活をしていると、
新学期にはかならず面談とともに「心臓病管理指導表」というのを提出します
今回診察に行って主治医に書いてもらいました
うちは今は学校に行っていないので、形だけの提出になっていますが、
学校の先生方は「管理指導表」に基づいて、
体育の授業や行事の参加などを考慮してくださいます
その都度相談したり、保護者がつき添ったり、ということも多いようです
同じ病名でも症状は個人でまったく異なり、まして心疾患の病名はたくさんあるので、
(自分の子どもの病名だけでも難しいです)
管理指導表があっても、個人個人で学校と相談しながら学校生活を送る必要があります
学校側も何かあったら大変なので、そのあたりはプレッシャーかもしれません
でも、「何かあると怖いから」、「困るから」、というような理由で、
何もさせてもらえない、という事例もあるようです
それでは、本来子どもができるであろう経験を奪ってしまうことになりかねず、
どこまでできて、どこまでできないかは、実際体験してみないとわからないことなので、
様子を見つつ、いろんな経験をさせてあげてほしいと思います
かく言うわたしも、
やっぱり子どもが小さかった頃は、
(いや、わりと最近まで、)
どうしても心配で、子どもの行動にいろいろと制限つけてました
小さい頃は毎日公園で遊ばせるというのは日課にしてましたが、
(多少の雨でもカッパ着せて連れてってました)
体を動かすこと、疲れそうなこと、はなるべくさせず、、、
だから公園までの行き帰りはベビーカーでしたし、
走りたそうなのを走らないで歩かせたり、
歩くの疲れたそぶりを見せたらすぐにだっこしたり、
いつもいつも子どもの行動を気にしていました
結局、本来できたかもしれない経験をしてこなかったことが多く、
経験値が足りないことで、
少し大きくなってから、本人がいろんな場面で、
困ったり、自信が持てなかったり、という原因になってしまったかな、
と反省です
今は成長して、自分の体調をだいぶ説明できるようになってきたので、
ずいぶん安心です
経験という面では遅ればせながら、本人がしたいと思うことは制限せずに、
できる限り経験できるようにと思っています
乗馬もそのひとつです
主治医からは、
走るよりも歩くことが大事、たくさん歩いてね、と言われています
足は第二の心臓で、歩くことによって心臓の循環の助けになります
うちの子の心臓の状態だと、
心臓のポンプの力を借りずに血液循環がされている(だらだらと流れ続けている)ので、
とくに足などは血流が戻りにくいのですが、
歩くこと、足を使うことが血流を押し上げる力になるようです
乗馬の良いところは、やっぱり足を使ってることかなと思います
体幹も鍛えられているようですし
乗馬をする前は、体がふにゃふにゃしてる感じだったのですが、
馬に乗るようになって、ふにゃふにゃ感がなくなりました
それに、大きな動物と意思を通わせることで、いろんな学びがあるようです
乗馬に出会えてよかったな~って本当に思います
ちなみに、子どもの管理指導表の指導区分はDです
Dは中等度の運動は「可」
・・・・
「中等度の運動」とは、
同年齢の平均的生徒にとって、少し息が弾むが息苦しくはない程度の運動
パートナーがいれば楽に会話ができる程度の運動であり、原則として、身体の強い接触を伴わないもの
等尺運動は「強い運動」ほどの力を込めて行わないもの
・・・・
「強い運動」とは、
同年齢の平均的生徒にとって、息が弾み息苦しさを感じるほどの運動
等尺運動の場合は、動作時に歯を食いしばったり、大きな掛け声を伴ったり、動作中や動作後に、顔面の紅潮、呼吸速迫を伴うほどの運動
・・・・
要するに心臓に負担がかかるかどうか、というところだと思います
Dなので、短距離走、長距離走、競泳、遠泳、球技の試合などは、
しないほうがいい、という感じでしょうか
でも例えば運動会で走りたいと思っているようなら、
スタート位置をずらすとかの考慮をしてもらって走ることで、
本人の参加したいという気持ちが納得できたら、
それも自信につながるのかなとは思います
どうしても運動系には自信を持てないことが多いですから、、、
まあ、うちの子は走りたい子ではなかったので、走ってませんが、、、
そんなこんなで、次回診察の9月はカテーテル検査で2泊3日の入院です
3歳の時のTCPC手術以来なので、どうなることやら、、、
今回エコーで確認してもらった心臓の状態は良好なようですし、
特に何か問題があるからカテをするわけではなく、
手術から10年以上たっているので、
外からはわからない、なかの状態を見てみましょう、
ということらしいです
あとは側副血管ができていたらコイルを詰めるそうです
側副血管は心臓の負担になるようなので
将来のリスクを減らすためにできることはしておきましょう
この子の心臓なら長生きできるよ~
と主治医
ありがとうございます
小児慢性特定疾病医療受給者証
2015年09月27日
今日は満月、中秋の名月、スーパームーンだそうです
(満月のスーパームーンは28日でした!)
「小児慢性特定疾病医療受給者証」
というのがありまして、
現在の受給者証の期限が9月末、
ということで、
継続の人は9月末までに保健所に申請しなくてはいけないのです
5月半ばに申請用紙が届いていて、
6月から7月に集中申請期間というのがあって、
ほとんどの人はその頃には申請するのですが、
わたしは毎年ぎりぎりでして、
今年もやっぱりぎりぎり。。。
9月初めに東京の病院に行って、子どもが診察を受けて、
お医者さんに医療意見書を書いてもらうお願いをして帰ってきました
で、今日やっと病院から医療意見書が届きました
ということは、9月末まであと3日しかないのです~
明日行けるといいのだけれど。。。
で、届いた医療意見書。。。
今回から病院の形式で書いていただいているので、
今までの意見書に書いてないこともあったりして、
ああ、そうなんだ!って新たな発見があったり、
(すみません、ちゃんと知らなかったことありましたです。。。)
手術の経緯、
最近は説明することもなくて久しぶりに確認したのですが、
ほんと、
うちの子、
生後5日でこんな手術に耐えたんだな~
よく生きながらえてくれたな~
なんて。。。
手術室に行く前の光景を思いだして
じんわり涙ぐんでしまいました。。。
この子は生きようとする力、生命力があったんだな、って。
<病名>
大分類、細分類:単心室症
副病名1:大動脈弓離断症、大動脈弁弁下狭窄
副病名2:心室中隔欠損症
<検査所見>
心電図:洞調律、左軸偏位、完全左脚ブロック (←と書かれていてもよくわからないデス)
など
肺動脈狭窄あり
など
フォンタン型修復術後右心バイパス単心室循環(←そんな名前なのだと初めて知りました。。。)
<経過>
2001/10
誕生
2001/10
D-K-S手術
右室ー肺動脈バイパス手術
大動脈弓修復術
心房中隔欠損作成術(←穴開けてたってすっかり忘れてました。。。)
2002/7
左BTシャント術
2003/11
両方向性グレン手術
2005/1
体肺動脈側副血管コイル塞栓術
2005/1
TCPC手術
2006/4
○○的バルーン肺動脈拡張術
↑読めなかった。。。
★☆★☆
そんなこんなで、もうすぐ14歳
元気に楽しく馬に乗ってます♪
毎日を楽しく生きていてくれるだけで、
ほんと、うれしいことです
(満月のスーパームーンは28日でした!)
「小児慢性特定疾病医療受給者証」
というのがありまして、
現在の受給者証の期限が9月末、
ということで、
継続の人は9月末までに保健所に申請しなくてはいけないのです
5月半ばに申請用紙が届いていて、
6月から7月に集中申請期間というのがあって、
ほとんどの人はその頃には申請するのですが、
わたしは毎年ぎりぎりでして、
今年もやっぱりぎりぎり。。。
9月初めに東京の病院に行って、子どもが診察を受けて、
お医者さんに医療意見書を書いてもらうお願いをして帰ってきました
で、今日やっと病院から医療意見書が届きました
ということは、9月末まであと3日しかないのです~
明日行けるといいのだけれど。。。
で、届いた医療意見書。。。
今回から病院の形式で書いていただいているので、
今までの意見書に書いてないこともあったりして、
ああ、そうなんだ!って新たな発見があったり、
(すみません、ちゃんと知らなかったことありましたです。。。)
手術の経緯、
最近は説明することもなくて久しぶりに確認したのですが、
ほんと、
うちの子、
生後5日でこんな手術に耐えたんだな~
よく生きながらえてくれたな~
なんて。。。
手術室に行く前の光景を思いだして
じんわり涙ぐんでしまいました。。。
この子は生きようとする力、生命力があったんだな、って。
<病名>
大分類、細分類:単心室症
副病名1:大動脈弓離断症、大動脈弁弁下狭窄
副病名2:心室中隔欠損症
<検査所見>
心電図:洞調律、左軸偏位、完全左脚ブロック (←と書かれていてもよくわからないデス)
など
肺動脈狭窄あり
など
フォンタン型修復術後右心バイパス単心室循環(←そんな名前なのだと初めて知りました。。。)
<経過>
2001/10
誕生
2001/10
D-K-S手術
右室ー肺動脈バイパス手術
大動脈弓修復術
心房中隔欠損作成術(←穴開けてたってすっかり忘れてました。。。)
2002/7
左BTシャント術
2003/11
両方向性グレン手術
2005/1
体肺動脈側副血管コイル塞栓術
2005/1
TCPC手術
2006/4
○○的バルーン肺動脈拡張術
↑読めなかった。。。
★☆★☆
そんなこんなで、もうすぐ14歳
元気に楽しく馬に乗ってます♪
毎日を楽しく生きていてくれるだけで、
ほんと、うれしいことです
東京で診察
2015年09月08日
金曜から2泊で東京に行ってきました
子どもの病院診察です
2泊なので、犬2匹も連れて、車で行きました
金曜11時半に出発して、休憩2回、
ちょっと平均速度早かったかな~な感じで、
夕方5時くらいに実家のある町田に到着
割と近くに圏央道ICができたので、短縮できたのかも~
金曜は犬たちの散歩して、ご飯食べて、すぐ寝ました
土曜、午前に病院、
午後は実家の庭仕事、
夜はばあばの退職祝いのお食事会、
なかなか忙しい土曜日でした
日曜は11時には実家を出て滋賀へむかいました
2泊3日ですが、観光もなにもない東京行きです
いつもだいたいそうなります
(あ、近場でお食事会はあったけど)
まあ、都心は人が多くて苦手なので、
近所で犬の散歩、で十分な感じです
さて、病院、
3か月くらいを目安に来てね、と言われてますが
この前が4月だったので、5か月たってしまいました
今回は子どもが大嫌いな血液検査がありました
以前に座って採血したら気分が悪くなったので、
ここ数回はベッドに寝て採血してもらっています
それからいつものレントゲンと心電図検査、
そして診察です
心臓専門の病院なので、
大学病院みたいに患者さんがいっぱいで
待合室が混み合って大変!ということはないのですが、
それでも、
10時半の予約で検査のために10時に来ても、
診察は11時過ぎになるくらいなので、
ひたすら待つことには変わりありません
診察では主治医がまず問診
もう中学生なので親の私にではなく子ども本人に聞きます
私でも自分の体の状態を的確に伝えるのは難しいので、
子どもの代わりについ答えてしまいそうになりますが、
親の場合はどんな状態なのかは見た目でしか判断できないので、
やっぱり自分でちゃんと伝えられるように、
本人が経験を積んでいくしかないのだなあと思います
なので、何年後になるかわからないけど
将来ひとりで診察に来られるようになるために、
親は黙って見守ります
(大事なことを言い忘れてたら言いますが)
それから聴診して、エコー検査
エコーは何度見てもよくわかりません
血液の流れとか、血管の様子とか見えるのがとても不思議です
血液検査の結果、
フォンタン循環で気になる肝機能に関する数値はおおむね良好
ɤ-GTPだけが少し高かったのですが(9-30のところ、35)
心配いらない範囲だそうです
心臓の状態が悪くなると上がるという数値(NT-pro BNP)が
とっても低いのがよかった、と言ってもらえました
(125以下のところ、26.9でした)
数字で見えると一安心
乗馬で心臓に負担がかかってないか心配でしたが、
乗馬のおかげでよい数値なのかも?
よかったです
ほかの検査も特に気になる変化もないようでした
前の手術から10年経つので、
一年後の来年秋にはカテーテル検査をしましょう、
ということになりました
久しぶりの入院になるので、
今から親の私が緊張してしまいます
さてさて、東京往復、移動は車とはいえ、
子どもはやっぱりずいぶん疲れたようで、
月曜、火曜はどこにも行かずゆっくりしています
次回診察は冬
新幹線で日帰りのほうがいいかな???
子どもの病院診察です
2泊なので、犬2匹も連れて、車で行きました
金曜11時半に出発して、休憩2回、
ちょっと平均速度早かったかな~な感じで、
夕方5時くらいに実家のある町田に到着
割と近くに圏央道ICができたので、短縮できたのかも~
金曜は犬たちの散歩して、ご飯食べて、すぐ寝ました
土曜、午前に病院、
午後は実家の庭仕事、
夜はばあばの退職祝いのお食事会、
なかなか忙しい土曜日でした
日曜は11時には実家を出て滋賀へむかいました
2泊3日ですが、観光もなにもない東京行きです
いつもだいたいそうなります
(あ、近場でお食事会はあったけど)
まあ、都心は人が多くて苦手なので、
近所で犬の散歩、で十分な感じです
さて、病院、
3か月くらいを目安に来てね、と言われてますが
この前が4月だったので、5か月たってしまいました
今回は子どもが大嫌いな血液検査がありました
以前に座って採血したら気分が悪くなったので、
ここ数回はベッドに寝て採血してもらっています
それからいつものレントゲンと心電図検査、
そして診察です
心臓専門の病院なので、
大学病院みたいに患者さんがいっぱいで
待合室が混み合って大変!ということはないのですが、
それでも、
10時半の予約で検査のために10時に来ても、
診察は11時過ぎになるくらいなので、
ひたすら待つことには変わりありません
診察では主治医がまず問診
もう中学生なので親の私にではなく子ども本人に聞きます
私でも自分の体の状態を的確に伝えるのは難しいので、
子どもの代わりについ答えてしまいそうになりますが、
親の場合はどんな状態なのかは見た目でしか判断できないので、
やっぱり自分でちゃんと伝えられるように、
本人が経験を積んでいくしかないのだなあと思います
なので、何年後になるかわからないけど
将来ひとりで診察に来られるようになるために、
親は黙って見守ります
(大事なことを言い忘れてたら言いますが)
それから聴診して、エコー検査
エコーは何度見てもよくわかりません
血液の流れとか、血管の様子とか見えるのがとても不思議です
血液検査の結果、
フォンタン循環で気になる肝機能に関する数値はおおむね良好
ɤ-GTPだけが少し高かったのですが(9-30のところ、35)
心配いらない範囲だそうです
心臓の状態が悪くなると上がるという数値(NT-pro BNP)が
とっても低いのがよかった、と言ってもらえました
(125以下のところ、26.9でした)
数字で見えると一安心
乗馬で心臓に負担がかかってないか心配でしたが、
乗馬のおかげでよい数値なのかも?
よかったです
ほかの検査も特に気になる変化もないようでした
前の手術から10年経つので、
一年後の来年秋にはカテーテル検査をしましょう、
ということになりました
久しぶりの入院になるので、
今から親の私が緊張してしまいます
さてさて、東京往復、移動は車とはいえ、
子どもはやっぱりずいぶん疲れたようで、
月曜、火曜はどこにも行かずゆっくりしています
次回診察は冬
新幹線で日帰りのほうがいいかな???